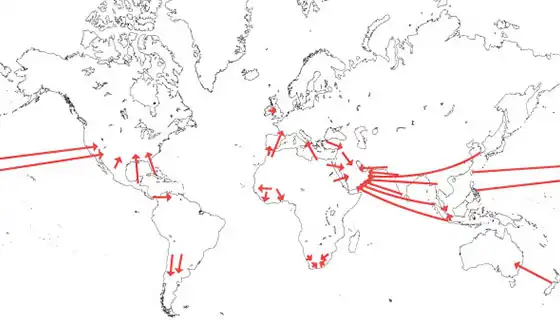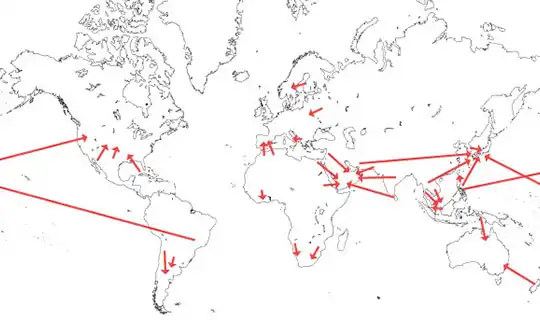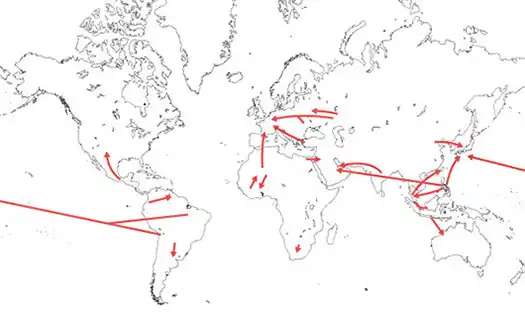国際的な人口移動
移民の呼称
歴史のなかで人々は様々な理由で外国に移住しました。
外国に移住した人々には、次のような呼称があります。
- 華僑
中国からの移民で、中国国籍を保有
現地の国籍を取得した場合は華人と呼称
- 印僑
イギリス植民地時代のインドからの移民
- ガストアルバイター
1960年代、ドイツが労働者不足を補うために協定を結び、トルコから受け入れた外国人労働者
「一時的な労働者」という扱いで、いずれ帰国する存在という扱いだったが、協定停止後も滞在を続けて問題化
- 日系人
日本人の海外移住者の子孫
1990年以降、南米のブラジル・ペルーからは雇用を求めた日本への移動が増加
1960年頃
低所得の地域から、雇用機会のある高所得地域のアメリカやヨーロッパへ移動が見られました。
国際的な人口移動(1960年頃)
1970年頃
戦後の経済復興から発展に移行したヨーロッパ諸国に、次のような移動が見られました。
- トルコからドイツへ
- ポルトガルや西アフリカの旧植民地アルジェリア・チュニジアからフランスへ
- アイルランドやインドからイギリスへ
国際的な人口移動(1970年頃)
1980年頃
1973・1979年の2度の石油危機で先進国の経済が停滞するなか、経済成長を始めた西アジアの産油国への移動が見られました。
受け入れる労働者を「単身者」という条件にしたので、これらの国では男性数が多くなりました。
国際的な人口移動(1980年頃)
アラブ首長国連邦の人口ピラミッド(2021年)
サウジアラビアの人口ピラミッド(2021年)
クウェートの人口ピラミッド(2021年)
1990年頃
1990年、日本で入国管理法が改正されました。
以前は未熟練労働者の入国を認めていませんでしたが、日系3世までは就労可能になりました。
これにより、南米のブラジル・ペルーなどから入国が多くなりました。
国際的な人口移動(1990年頃)
2000年頃
経済成長する地域への人口移動が次のように見られました。
- EUに加盟した東欧からの移動
- ASEAN域内での移動
- 産油国への移動
国際的な人口移動(2000年頃)
日本への入国
法・制度の改正
1990年、
入国管理法改正
以前は単純労働者の入国・定住を認めなかったが、日系3世まで家族含めて就労可能に変更
南米のブラジル・ペルーなどから入国が増加し、輸送用機械の多い東海地方の愛知県(トヨタ)・静岡県(ヤマハ・スズキ)、関東地方の神奈川(日産)・群馬県(スバル)に居住しています。
1997年、外国人技能実習制度の改正
以前は1年間の「研修」と技術向上の1年間の「特定活動」としていたが、「特定活動」を2年に延長
中国やフィリピン・ベトナムからの流入が増加しました。
日本の国籍別外国人登録者
日本の国籍別外国人登録者の推移
都道府県別・国籍別在留外国人人口(2019年)
韓国・朝鮮籍
1910年の韓国併合以降、朝鮮半島の人々は日本国籍となりました。
終戦後、日本に在住する朝鮮人は韓国・朝鮮籍に変更されました。
歴史のなかで商工業の発達した大阪に集まり、現在も多くの者が在住しています。
中国籍
労働・留学目的で居住する者が増加しています。
フィリピン国籍・ブラジル国籍・ペルー国籍
法・制度の改正で居住する者が増加しました。
アメリカ国籍
米軍基地が立地する沖縄で多くの人が居住しています。
労働
女性の社会進出
日本
男女共通
日本の男女共通の特徴は、欧米諸国に比べて大学進学率が高いことです。
その分就業時期が遅くなり、15~19歳の就業率が下げります。
女性
男性に比べ、女性は結婚や出産を機に離職し、育児がひと段落した後に再び働きます。
日本に見られるこの特徴は、グラフの形からM字カーブと言います。
男女の年齢別労働力率(2020年)
欧米諸国
欧米諸国では出産・育児に関わらず就業を続けられるようにして、M字カーブの解消に努めています。
従って、男女の就業率の差が小さくなります。
途上国
女性は雇用機会がまだ乏しく、社会進出が遅れています。
特にイスラム圏では女性の社会的地位が低く、男性の教育が優先されています。
賃金
国民総所得(GNI)
「1人当たりの国民総所得(GNI)」≒「1人当たりの年収」≒「各国の経済水準」と考えます。
また、入試においては、他に国民総生産(GNP)、国内総生産(GDP)という表現も出てきますが、国民総所得(GNI)とほぼ同じ意味と考えるとよいです。
産業別に国民総所得(GNI)に占める割合を見ると、基本的には第3次産業>第2次産業>第1次産業となります。
また、経済の発達に伴って第1次産業人口が減少し、第2次・第3次産業人口が増加します。
つまり、先進国ほど国民総所得(GNI)が高くなります。
1人あたりのGNI(2018年 単位:ドル)
| 国名 |
ドル |
| スイス |
83580 |
| ノルウェー |
80790 |
| ルクセンブルク |
77820 |
| アメリカ合衆国 |
62850 |
| カタール |
61190 |
| アイスランド |
60740 |
| デンマーク |
60140 |
| アイルランド |
59360 |
| シンガポール |
58770 |
| スウェーデン |
55070 |
| オーストラリア |
53190 |
| オランダ |
51280 |
| オーストリア |
49250 |
| フィンランド |
47820 |
| ドイツ |
47450 |
| ベルギー |
45430 |
| カナダ |
44860 |
| 日本 |
41340 |
各国のGNI
北欧
人口1人当たりのGNIが高い先進国では、社会保障が充実しています。
社会保障が充実する北欧諸国は、やはり表にあるように人口1人当たりのGNIが高いです。
スイス
スイスは、チューリヒなどに金融・保険業が集積し、金融サービス部門に特化して経済水準が極めて高いです。
人口1人当たりのGNIは、先進国の中でもトップクラスに高いです。
日本
日本の人口1人当たりのGNIは、先進国としてのイメージから高いと思われますが、スイスの半分以下に過ぎません。
入試ではスイスと日本の値のどちらかを覚えておくと応用可