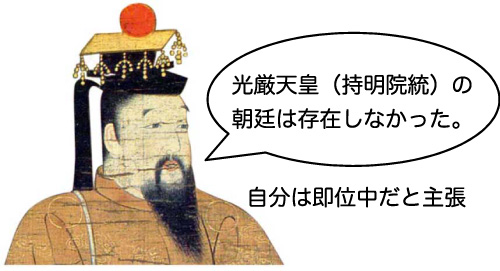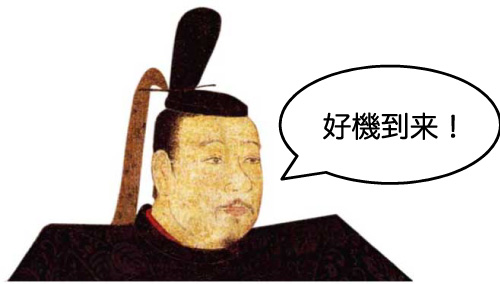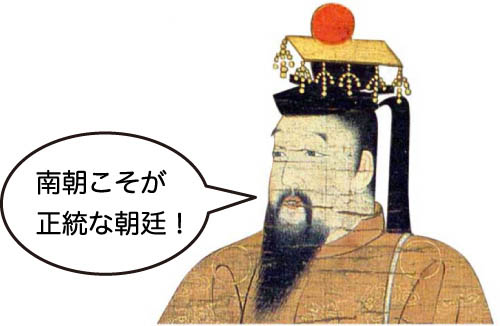概要
鎌倉幕府の倒壊後、後醍醐天皇は幕府が擁立した光厳天皇の存在を否定し、再度政治を開始しました。以後の後醍醐の治世を「建武の新政」と称します。延喜・天暦の治を理想として天皇の権限集中を図りましたが、貴族・武士・農民の反発を招きました。やがて中先代の乱が起こると、足利尊氏は公然と後醍醐に反旗を翻しました。
束の間の新政
新しい政治の開始
後醍醐天皇は光厳天皇を否定し、自分が即位中だと主張しました。
年号を「建武」とし、建武の新政と呼ばれる政治を始めました。

後醍醐天皇
(統)
建武の新政の機構
建武の新政
天皇に権限を集中しました(院・摂政関白否定)。
重要政務を担う記録所や、土地問題を取り扱う雑訴決断所が、中央に再興・設置されました。
訴訟・土地所有の確認なども含めて、最終決定に天皇の綸旨
を必要としました。
記録所・雑書決断所以外の機構
| 中央 |
|
| 地方 |
鎌倉将軍府
関東の統治機関(成良親王・足利直義) 陸奥将軍府
奥州の統治機関(義良親王・北畠顕家
) 諸国では 国司・守護を併置
|
新政への不満
貴族・武士・農民など広い層から批判・不満の声が出ました。
民衆の思いを代弁する800余字の落書(風刺)として、二条河原落書が掲げられました。
二条河原落書
作者未詳ですが、七五調・言葉・批判精神から、作者はかなりの知識人と分かります。
新政の崩壊
1335年、中先代の乱
北条高時の遺児北条時行が鎌倉を占領した事件
足利尊氏は反乱を鎮圧すると、鎌倉で新政権の組織化を進め、新政に公然と反旗を翻しました。
足利高氏
1336年、尊氏は京都を制圧して持明院統から光厳上皇の弟光明天皇を即位させました。
他方、後醍醐天皇は奈良の吉野へ逃れ、自らの皇位を主張しました。
持明院統による京都の朝廷北朝と、大覚寺統による吉野の朝廷南朝が並び立ちました。
以後、2つの朝廷が対立する南北朝の動乱が約60年間続きました。
後醍醐天皇