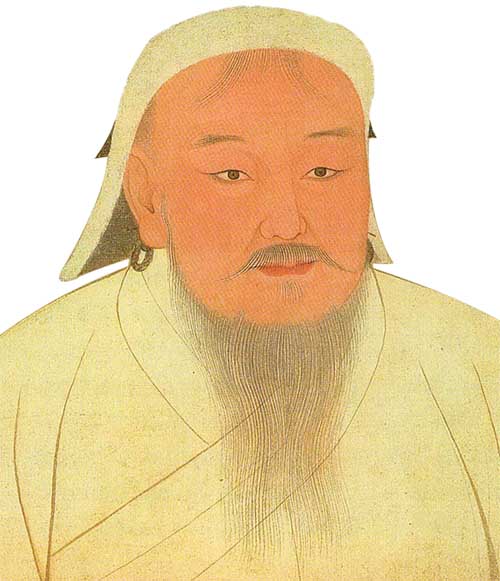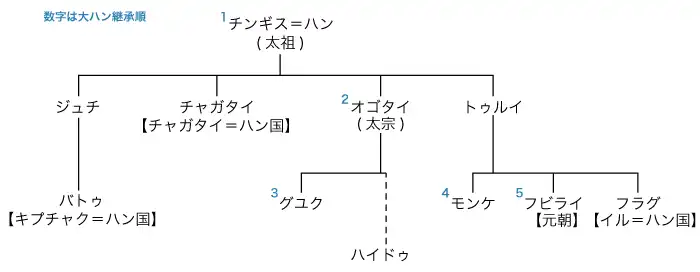概要
13世紀初頭にチンギス=ハンが建国したモンゴル帝国は、破竹の勢いで勢力を拡大し、ユーラシア大陸の東西を支配していきました。モンゴル帝国は、極東や東南アジアにも勢力を広げようと、日本などに遠征しました。また、交通路を整備したため、東西交流が盛んにおこなわれました。ヨーロッパ諸国からは、恐れられる一方で、イスラーム勢力を打倒できると期待され、使者が派遣されました。
モンゴル帝国
モンゴル帝国の建国
12世紀、遼が滅亡すると、モンゴル高原では分裂の動きが一時期強まりました。
モンゴル部族出身のテムジンは、諸部族を支配下に収め、1206年、遊牧民の集会クリルタイ
で遊牧民の君主を意味するハン
の位につきました。
ハンの位についたテムジンは、チンギス=ハンと号し、モンゴル帝国
(大モンゴル国)を建てました。
クリルタイ
モンゴル帝国のハンは、この集会で選出される仕組み
ハン
便宜上、以降の内容では皇帝を指す意味で「大ハン」、その他王族を指す意味で「ハン」を使用
チンギス=ハン
クリルタイで即位するテムジン(チンギス=ハン)
領域の拡大
チンギス=ハン
チンギス=ハンは、全遊牧民を1000戸単位に編成した軍事・行政組織千戸制
を創始しました。
チンギス=ハンは、中央アジアのナイマンやホラズム朝
(ホラズム=シャー朝)を滅ぼし、西北インドに侵入しました。
モンゴル帝室の系譜
オゴタイ
チンギス=ハンの死後、子オゴタイは兄弟・一族たちとの争いに勝利し、1229年、大ハンの位につきました。
オゴタイは、金を滅ぼして華北を領有し、また、モンゴル高原のカラコルム
に都を建設しました。
バトゥ
13世紀、チンギス=ハンの孫バトゥ
が、ロシア
を征服しました
。
さらにバトゥはヨーロッパに侵入しました。
1241年、
ワールシュタットの戦い
バトゥがドイツ・ポーランド連合軍を破り、ヨーロッパ諸国を脅かした戦い
フラグ
1258年、チンギス=ハンの孫フラグ
は、バグダードを攻略し、アッバース朝
を滅ぼしました。
チンギス=ハンの子孫の地方政権
13世紀半ばまでに広がったモンゴルの支配領域に、チンギス=ハンの子孫たちが、次の地方政権をつくりました。
モンゴル帝国は、これら地方政権が、大ハンのもとに連合するという形をとりました。
しかし、大ハンの位をめぐる争いも時に生じました。
1266~1701年、
ハイドゥの乱
ハイドゥが、モンゴル帝国でフビライ=ハンの大ハン即位に反対して起こした反乱
モンゴル帝国の図解
モンゴル帝国-フビライ=ハンの治世
元の成立
1260年、フビライ
が第5代の大ハンに即位し、都を現在の北京
である大都
に移しました。
1271年、フビライは国号を中国風の元
(大元ウルス)と定めました。
1276年、元は南宋を滅ぼし、中国全土を支配しました。
フビライ=ハン
元の遠征
元はモンゴル高原と中国を領有し、また、チベット・高麗を属国としました。
元は交易圏拡大を目指し、パガン朝
が支配するビルマ(ミャンマー)に進出しました。
一方、ヴェトナム(大越)にも出兵しましたが、陳朝
により撃退されました。
他地域にも遠征軍を送りましたが、ジャワ・日本を属国にできませんでした
。
モンゴル軍との戦争後、ビルマではパガン朝が滅亡
元の中国統治
元の支配下では、モンゴル人
第一主義が採られ、次いで西域出身の色目人が重用され、漢人(中国人)が蔑視されました
。
これに伴い、科挙はほとんど重視・実施されず
、士大夫は官僚になる道を事実上閉ざされました。
元の交易
陸上交易
元は、幹線道路に沿って馬を乗り継ぐ駅を設ける、ジャムチ
と呼ばれる駅伝制
を施行しました。
結果、東アジアからヨーロッパにいたる陸上交易が発達しました。
海上交易
中国の杭州・泉州などの港市が繁栄しました。
貨幣
貨幣として銅銭・金・銀が用いられました。
フビライ=ハンが交鈔
と呼ばれる紙幣を発行し、元の主要な通貨となりました。
銅銭
使用されなくなった銅銭が日本に流出し、その貨幣経済の発達を促進
文字
モンゴル帝国内では漢語からトルコ語・ラテン語まで様々な言語が用いられました。
フビライ=ハン
の命令で、チベット仏教僧
パスパが公用文字パスパ文字
を作成し、元でのモンゴル語の表記に用いられました。
パスパ文字は後に廃れ、モンゴル語はウイグル文字で表記
文化
元曲
元代に完成した古典演劇(戯曲)元曲
が、庶民に愛好されて盛んになりました。
元曲の代表作として、『西廂記
』『琵琶記
』などが作られました。
小説
『水滸伝
』などの大長編小説の原型が著されました。
モンゴル帝国の解体
14世紀、モンゴル帝国内で内紛が生じました。
チャガタイ=ハン国でティムールが勢力を伸ばし、イラン・イラクまで領土を広げました。
キプチャク=ハン国ではモスクワ大公国が勢力を伸ばしました
元の末期、宮中での権力闘争や経済政策の失敗が続き、各地で民衆が蜂起しました。
1351~66年、
紅巾の乱
宗教結社白蓮教
を主体とした農民反乱
1368年、紅巾の乱の中から台頭した朱元璋が、明を建国しました。
同年、元は明軍に大都を奪われ、モンゴル高原まで退きました。
モンゴル帝国の東西交流
東方への関心
イスラーム勢力と争っていた西ヨーロッパで、東方でその勢力を抑えるモンゴル帝国に関心がもたれました。
また、1241年にモンゴル軍がポーランド・ドイツ連合軍を破ると、攻撃中止の交渉と敵情視察が必要になりました。
公的な訪問
ローマ教皇によって
プラノ=カルピニ
が、フランス王
ルイ9世
によってルブルック
が、モンゴル帝国に派遣されました。
商業的な訪問
ヴェネツィア
の商人マルコ=ポーロが元の大都を訪れ、フビライ=ハンに仕えました。
マルコの見聞をまとめた『世界の記述
(東方見聞録)』はヨーロッパで反響を呼びました。
イスラーム化
キプチャク=ハン国やイル=ハン国の君主は、イスラームに改宗し、イスラム教を保護しました
。
次第に中国本土でもイスラームが広がりました。
この動きとともにイスラームの学問・文化も流入しました。
天文学
中国の元
の時代に、フビライ=ハン
の命で、郭守敬
がイスラームの天文学の影響を受けて
授時暦
を作りました。
元代の授時暦は、江戸時代の日本の貞享暦の基礎となりました。
キリスト教の布教
初期のイル=ハン国は、キリスト教のネストリウス派を保護し、ヨーロッパ諸国やローマ教皇庁と交流しました。
13世紀末、モンテ=コルヴィノ
がフビライの時代の大都(北京)を訪れ、カトリックの布教に努めました。
モンゴル帝国内の文化交流
元からイル=ハン国に伝わった中国絵画が、細密画(ミニアチュール)に影響を与えました
。